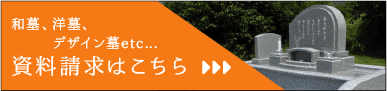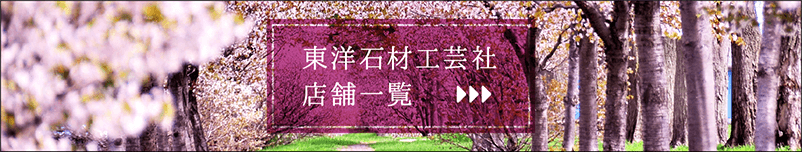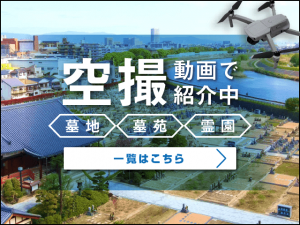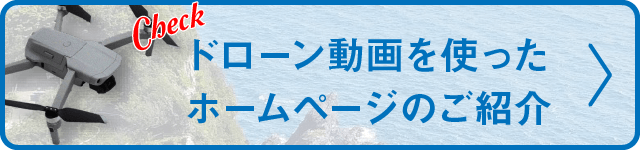お役立ちコラム
3.202025
お墓の処分(墓じまい)・改葬に必要な許可とは?意外と知らない必要書類と手続きの流れ

自身の親や一族のお墓の管理、これからどうすべきか――――。そんなことをふと考える方も多いのではないでしょうか。昔は「お墓は代々守っていくもの」と言われてきましたが、今では核家族化や地方離れ、子ども世代のライフスタイルの変化により、お墓を受け継ぐこと自体が難しく、そのため「お墓じまい」や「改葬」を選ぶご家庭も年々増えているのも事実です。
そもそもお墓を処分(墓じまい)または改葬するのにはどんな許可が必要なのでしょうか。
■後継者がいない!? 今後お墓をどう管理していけばいいのか
 お墓に関する悩みの中で特に増えているのが、「後継者がいない=墓守がいない」という問題です。子どもがいないご家庭や、子どもが遠方に住んでいて管理が難しいなどは一時的な問題ではありません。そのため現在建っているお墓を処分(墓じまい)して、永代供養墓や合祀墓といった、後継者=墓守がいなくても安心して任せられる供養方法を検討する必要があります。
お墓に関する悩みの中で特に増えているのが、「後継者がいない=墓守がいない」という問題です。子どもがいないご家庭や、子どもが遠方に住んでいて管理が難しいなどは一時的な問題ではありません。そのため現在建っているお墓を処分(墓じまい)して、永代供養墓や合祀墓といった、後継者=墓守がいなくても安心して任せられる供養方法を検討する必要があります。
また、ご自身が墓守を担っている場合、生前のうちに自身の希望やお墓のこれからのことを、ご家族に伝えておくことで残された方たちの負担も軽減されます。
■意外な落とし穴!? 改葬や「墓じまい」は勝手にできない?
 改葬やお墓の放棄(墓じまい)は、個人の判断だけで自由に進めることはできません。市区町村の役所から「改葬許可証」の取得が必須です。この許可証がなければ、ご遺骨の移動、納骨先での受け入れも認められません。また、お墓のある寺院や霊園の管理者に対しても、事前に手続きを行います。そうすることでお墓を処分(墓じまい)するための管理契約の解除や墓所の原状回復といった次に進めることができるのです。事前に何をしなければならないのか、しっかり調べてから「墓じまい」や「改葬」を進めていきましょう。
改葬やお墓の放棄(墓じまい)は、個人の判断だけで自由に進めることはできません。市区町村の役所から「改葬許可証」の取得が必須です。この許可証がなければ、ご遺骨の移動、納骨先での受け入れも認められません。また、お墓のある寺院や霊園の管理者に対しても、事前に手続きを行います。そうすることでお墓を処分(墓じまい)するための管理契約の解除や墓所の原状回復といった次に進めることができるのです。事前に何をしなければならないのか、しっかり調べてから「墓じまい」や「改葬」を進めていきましょう。
■墓じまい・改葬手続きの基本的な流れ
 では実際にお墓の処分(墓じまい)や「改葬」をすることになったらどのように進めていけばいいのでしょうか。
では実際にお墓の処分(墓じまい)や「改葬」をすることになったらどのように進めていけばいいのでしょうか。
✔️1.改葬先(新しい納骨先)を決める
改葬手続きの第一歩は、ご遺骨を納める新しい場所を決めることです。選択肢としては、永代供養墓や納骨堂、樹木葬、公営墓地など多様化しています。後継者がいない場合や、管理の負担を減らしたい!という方に、寺院や霊園が供養を続けてくれる「永代供養墓」が人気となっています。また、供養先へのアクセスや費用、宗教・宗派の制限の有無なども比較ポイントです。将来的に家族の供養や訪問のしやすさを考慮し、ご家族と話し合いながら自分たちに合った納骨先を選ぶことが、後悔しない改葬につながります。
✔️2. 改葬先から「受入証明書」を取得する
新たな納骨先が決まったら、次に行うのが「受入証明書」の取得です。これは、改葬先となる墓地や納骨堂がご遺骨の受け入れを正式に認めたことを証明する書類で、市区町村に改葬許可を申請する際に必ず必要となります。受入証明書は、契約後に納骨先の管理者や事務所で発行してもらえます。発行までに数日かかることもあるため、事前に問い合わせて準備しておくとスムーズに手続きが行えます。
✔️3. 現在の墓地管理者に改葬の意思を伝える
改葬先の「受入証明書」を準備したら、現在墓地がある寺院や霊園の管理者に改葬の意向を伝えましょう。特に寺院墓地の場合、檀家を離れることになるため、丁寧な相談が必要です。トラブルを防ぐためにも、事情や背景をしっかり説明し、理解を得ましょう。また、改葬にあたっては「閉眼供養(魂抜き)」を行い、ご先祖様の魂をお墓から抜いて供養する必要があり、僧侶への依頼やお布施も必要なので、早めの手配がお勧めです。
✔️4. 市区町村に「改葬許可申請書」を提出する
改葬先の「受入証明書」がそろい、現在の墓地管理者との話し合いが済んだら、次は市区町村役所への申請です。具体的には、現在のお墓がある地域の市区町村役所に「改葬許可申請書」を提出します。申請書は役所の窓口で受け取れるほか、最近では自治体のホームページからもダウンロードできる場合もあるので一度チェックしてみてください。
✔️5. 改葬許可証の取得・ご遺骨の取り出し
市区町村から「改葬許可証」が発行されたら、いよいよお墓からご遺骨を取り出す作業に進みます。このタイミングで、あらかじめ手配していた僧侶による「閉眼供養(魂抜き)」の儀式を執り行い、ご先祖様の魂を丁寧に送り出します。儀式後、ご遺骨は納骨袋や骨壺に入れて丁寧に運び出します。
※墓地によっては、墓石を撤去する際に専門の石材業者へ依頼が必要となり、その費用も発生します(目安:10万〜30万円程度)。
✔️6. 改葬先への納骨・改葬手続きの完了
遺骨の搬送には特別な許可や車両は必要ありませんが、丁寧に扱うことが大切です。改葬先に到着したら、改葬許可証を提出し、正式に納骨を行います。納骨方法は、一般墓・納骨堂・合祀墓などにより異なるため、事前に確認しておきましょう。
納骨後、これで改葬手続きはすべて完了となります。ただし、元のお墓が寺院墓地などの場合は、檀家離脱の手続きやご挨拶など、最後まで丁寧な対応を心がけると良いでしょう。
■お墓を処分した後はどうすればいい?
 お墓を処分した後、「供養はどうするのか」「遺骨の行き先は?」と不安になる方も多いでしょう。処分=供養の終わりではなく、形を変えて供養を続けることが大切です。多くの方は、永代供養墓や納骨堂、樹木葬などへご遺骨を移して供養を継続しています。また、手元供養という方法もあり、自宅で小さな仏壇や骨壺を用いて故人を偲ぶことも可能です。お墓を処分した後も、気持ちの上での供養を大切にすることで、後悔のない選択ができます。家族と相談し、自分たちに合った供養の形を選びましょう。
お墓を処分した後、「供養はどうするのか」「遺骨の行き先は?」と不安になる方も多いでしょう。処分=供養の終わりではなく、形を変えて供養を続けることが大切です。多くの方は、永代供養墓や納骨堂、樹木葬などへご遺骨を移して供養を継続しています。また、手元供養という方法もあり、自宅で小さな仏壇や骨壺を用いて故人を偲ぶことも可能です。お墓を処分した後も、気持ちの上での供養を大切にすることで、後悔のない選択ができます。家族と相談し、自分たちに合った供養の形を選びましょう。
■まとめ
お墓の処分(墓じまい)や改葬は、故人を大切に思う気持ちから生まれる新しい供養の形です。後悔のない選択のために、事前の準備と家族との話し合いを大切に進めていきましょう。
もしお墓の処分(墓じまい)や改葬を考え始めたら、東洋石材にご相談ください。
「墓じまい」の費用は30万円(約6m²)からのプランをご用意しています。この価格には、墓石の撤去、ご遺骨の取り出し、墓地の更地化といった「墓じまい」に必要な基本的作業がすべて含まれている他にも、行政手続きの代行や、寺院・霊園との調整もスムーズに行えます。
さらにアフターフォローまでしっかりと行うほか、日本全国に提携する職人がいるので、どこででも「墓じまい」をトータルでサポートいたします。
またお墓の建墓や引っ越しも日本全国対応可能です。まずは、お気軽にお問い合わせください。
ご相談は無料で承っております。オンラインでの相談は、こちら